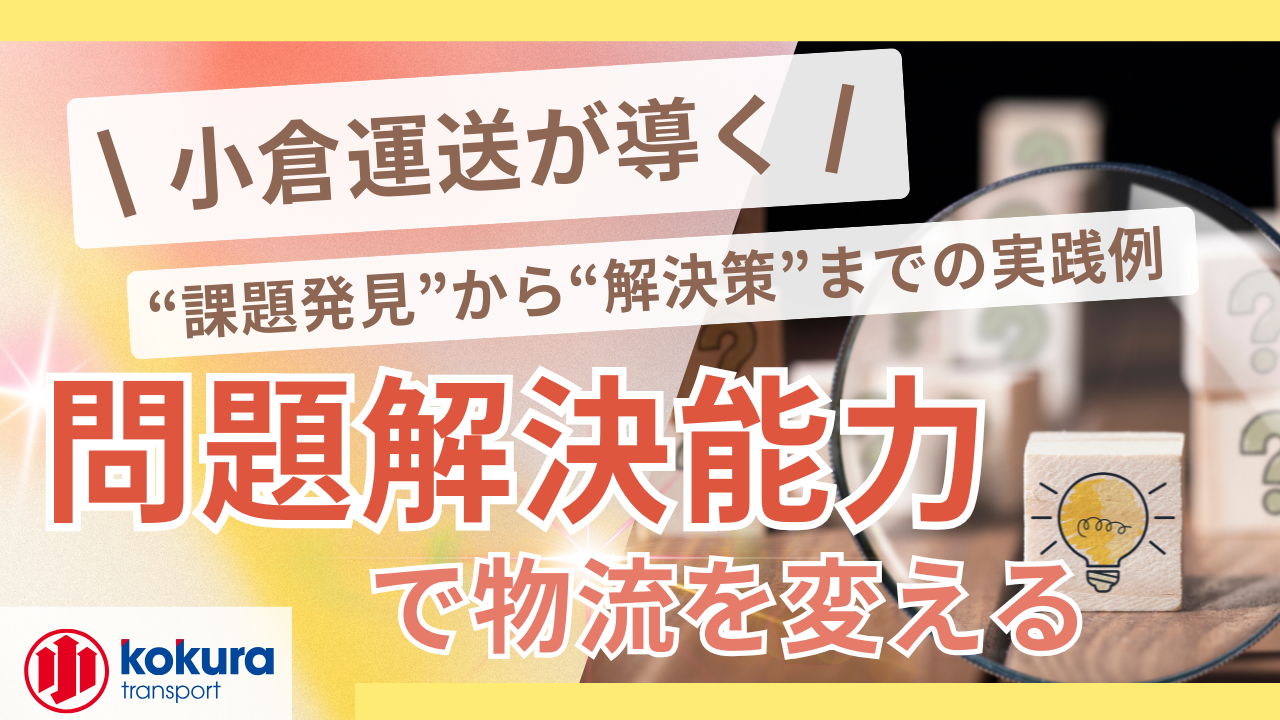
ビジネスの成長や企業競争力の維持には、常に変化する環境下で素早く課題を発見し、適切な解決策を打ち出す“問題解決能力”が不可欠です。とりわけ、物流業界は社会インフラとしての役割が大きく、モノを円滑に運ぶ仕組みが乱れると、多くの企業や消費者が不利益を被る可能性があります。社会全体のサプライチェーンが停止すれば、経済的なダメージだけでなく、生活物資が届かないなど人々の暮らしに直接影響を及ぼすからです。
小倉運送は、「モーダルシフト」「Sea&Rail輸送」「ラストワンマイル協同組合」といったキーワードを軸に、物流を“点”ではなく“線”や“面”として捉え、課題を明確化しながら最適解を導く“物流コンサル”を提案してきました。そこに深く根ざしているのが、現場と経営、そして地域と世界をつなぐ“問題解決能力”です。
本記事では、小倉運送の事例を手がかりに、物流コンサルで求められる問題解決能力のエッセンスを解説します。現場力とデータ分析、人材育成、地域密着など、多様な視点から紐解くことで、なぜ問題解決能力が企業や地域社会にとって強力な武器となり得るのかを考察していきます。
問題解決能力とは、「課題を正確に把握し、原因を追究し、具体的な手段を用いて解決まで導くプロセスを設計・実行する力」です。物流では、輸送手段の選択ミスがコスト増や納期遅延につながり、在庫管理の不備が販売機会損失を招くなど、ミスが即ビジネスリスクへ直結します。そのため、課題の発見と対応のスピードが非常に重要です。
小倉運送は長年の現場経験を通じて、トラック・鉄道・海上輸送などを自在に組み合わせるノウハウを構築してきました。これらの輸送モードごとの特性やコスト、環境負荷を分析し、荷主企業のビジネスニーズに応じた最適解を導くプロセスこそ、“問題解決能力”の具体例といえるでしょう。漠然と「トラックが不足している」という表面的な事象だけを捉えるのではなく、「なぜ不足し、どのようなモードシフトが有効か」を突き詰める姿勢が鍵となります。
製造業の現場では「現場・現物・現実」を重んじる“三現主義”が知られていますが、物流でも同様です。輸送車両や拠点を実際に目で見て、データだけではわからない問題を把握するアナログ的なアプローチは、デジタルの時代でも欠かせません。小倉運送の担当者は、クライアントの倉庫や工場へ足を運び、具体的にどのような作業手順があるのか、ボトルネックはどこにあるのかを丁寧に確認します。こうした「現場重視」の考え方は、的外れな対策を回避し、より実践的な解決策を生み出すための重要なステップなのです。
ひとくちに物流の課題といっても、その原因は多岐にわたります。ドライバー不足、燃料費の高騰、社会インフラ整備の遅れ、環境規制の強化など、個別要素の組み合わせによって問題が複雑化するのが特徴です。その複雑性を解きほぐすためには、環境・コスト・労働・ITといった多方面からのアプローチが不可欠なのです。
小倉運送のモーダルシフト提案には、鉄道や船を活用することでCO₂排出を減らす“環境視点”、長距離トラックドライバーの拘束時間を抑える“労働視点”、保管やリードタイムを最適化する“コスト視点”など、複数の観点が織り込まれています。問題解決能力を発揮するためには、一面的な対処ではなく、複合的に解決策を組み立てる柔軟性が求められるのです。
近年、さまざまな規制が見直されるなか、運送業界でも高速道路料金や燃料の課税制度、労働時間に関する法改正など、新たなルールが次々と導入されています。このとき、“問題解決能力”を発揮できる企業は、その法改正をチャンスに変える道を模索します。小倉運送は最新の法令情報を常にチェックしつつ、自社やクライアントが持つ経営資源を組み合わせ、新たなルート設計や輸送モードの切り替えによって恩恵を最大化する戦略を打ち出しているのです。
問題解決の第一歩は「正しい問題設定」にあります。しかしながら、物流の現場では膨大な作業工程やスタッフの動き、リアルタイムで移動する貨物など、把握しきれない情報が山積しています。そこで小倉運送が注力しているのが、現場力とデータ活用の融合です。
一例として、小倉運送では拠点間での在庫管理において、日々の入出荷データをリアルタイムに共有するシステムを利用しています。これにより、どの倉庫でどの製品がどれだけ保管され、どれだけ出荷されているかを一目で把握できるようになっています。問題が起きる前に傾向を察知し、作業負荷の平準化や倉庫間の在庫再配置など、予防的な対策を講じやすくなるのです。

物流の課題は、輸送会社だけで解決できるものではありません。サプライチェーンを構成するメーカー、卸、倉庫、販売店など、複数のプレイヤーが連動してこそ真の改善が可能になります。そのため、問題解決能力を高めるうえでは、サプライチェーン全体を俯瞰する視点が重要です。たとえば、メーカーが抱える生産調整や在庫方針が、物流会社にとって過度な負荷になっていないか。あるいは、販売店でのセールやイベントが倉庫出荷にどう影響しているか。こうした情報を総合的に管理できるかどうかが、効率化のカギを握ります。
小倉運送は倉庫管理や港湾運送、工場構内作業の請負など、チェーンの各段階に深く関わりながら、情報を横断的に把握しています。これにより「どの段階で在庫を持つか」「拠点間の輸送をどう組み合わせるか」といったマクロな視点で課題を整理し、最適解を提示できるわけです。局所的な対処にとどまらず、企業全体のビジネス戦略に合わせた輸送設計ができるのも、小倉運送の強みといえるでしょう。
さらに、北九州港をはじめとする国内外の港湾と連動することで、グローバルなサプライチェーンの設計にも貢献しています。海外メーカーとの生産調整や輸入貨物のタイムリーな配送計画など、多くのステークホルダーの意向を汲み取りながら、最適な物流設計を行う必要があります。国際輸送における通関や法規制、文化の違いなども踏まえ、包括的に調整できるのは“小倉運送ならでは”の総合力といえます。
ドライバー不足や燃料費高騰などの課題に対して、最も象徴的な解決策がモーダルシフトです。トラックだけでなく鉄道・海上輸送を組み合わせ、大量輸送によるコストメリットやCO₂排出削減を実現することで、企業と社会の両方に貢献します。
しかし、その実現には細やかな工程調整が欠かせません。鉄道やフェリーの運行ダイヤに合わせる必要があるため、荷主企業の生産計画や出荷タイミングを再設計するケースも生じます。小倉運送の強みは、こうした複雑な調整を“コンサル”という形で担い、環境負荷とコスト削減を両立させる発想力を提供できる点にあります。単なるアイデアだけでなく、具体的なスケジュール策定や荷役方法の提案まで踏み込む実行力もまた、問題解決能力の一端を示しています。
博多港を活用したSea&Rail輸送の事例では、海外から到着したコンテナを港湾でトラックに積み替えることなく、そのまま鉄道へ移行できる仕組みを整備し、コスト削減とリードタイム短縮を同時に実現しました。トラックドライバーの労働負荷を減らしつつ、長距離輸送を効率化できるため、荷主企業からは「納期の安定性が高まった」「運送コストが低減した」といった評価を得ています。こうしたモデルケースが増えれば、物流業界全体のサステナビリティ向上にもつながるでしょう。
在庫を「どこで」「どのくらい」持つかは、企業にとって大きなリスク管理上の課題です。特に、EC需要の拡大に伴い、小口出荷が頻発する現代では、倉庫オペレーションの効率が企業の収益を左右するケースも増えています。
小倉運送はクロスドッキング(TC)を活用した仕組みで、入荷から出荷までのリードタイムを短縮し、在庫を最小化する提案を行ってきました。ここでも鍵となるのは、荷主企業の販売計画や需要予測を深く理解したうえで、一連のフローをシームレスにデザインする能力です。単に倉庫のスペースを貸すだけではなく、「過剰在庫をどう減らすか」「繁忙期のピークをどう乗り切るか」といった根本課題を解決に導くのが、“物流コンサル”型の問題解決力といえるでしょう。
昨今はネット通販で、24時間365日いつでも注文が入る環境が当たり前になりました。便利になった半面、キャンペーン時などに注文が集中することで在庫管理が混乱するリスクがあります。小倉運送では、ピッキングシステムの自動化や作業の標準化を提案し、急激なオーダー増にも対応できる余力を確保する施策を提供しています。また、「在庫は持たないが売上は伸ばしたい」といったクライアントの要望に対しては、複数の倉庫を連携し最適な拠点に振り分ける“分散型在庫管理”を勧めるなど、柔軟なソリューションを提示するのも特徴です。
国際貨物の取り扱いや工場内作業の請負といった複数の領域で、現場の安全と効率を追求するのも小倉運送の特徴です。例えば、海外からの貨物をどのタイミングで取り扱い、どの倉庫へ振り分け、どのように検品・加工して国内拠点へ出荷するか――この一連の流れで発生する潜在的な課題を洗い出し、最適化する提案をまとめ上げるのは容易ではありません。
ここでの問題解決能力とは「最適な解決策を導き出す力」ともいえます。工場構内の動線を再設計し、フォークリフトの稼働時間を短縮し、安全性を高める。あるいは、港湾での荷役と倉庫での仕分けを統合して作業ロスを減らす。こうした視点は、どの企業にも備わっているわけではありません。サプライチェーンの要所で培った経験と調整力があるからこそ、生きた解決策が生まれるのです。
工場構内や港湾での作業は、多種多様なリスクが潜んでいます。大型機械や重機を扱うこともあれば、輸送の遅れが生産計画全体に影響することもあります。小倉運送では、作業手順を細かくマニュアル化するだけでなく、「なぜこの手順が必要なのか」という背景をスタッフに共有し、事故防止と効率化の両立を図っています。さらに、危険物取り扱いなどの特殊なノウハウを活かし、状況に応じたカスタムメイドの標準化を設計できる点も強みといえるでしょう。
物流現場の問題解決において、人材が果たす役割は絶大です。特に、現場を熟知したスタッフが自発的に課題を発見し、改善を提案できる組織風土は、持続的な競争力の源泉になります。
小倉運送ではOJTでの実地指導や、若手社員のアイデアを経営陣が積極的に取り入れる体制の整備を進めています。これによって、日々のオペレーションのなかで湧き上がる“小さな気づき”が、やがて大きな問題解決の糸口となるのです。人材育成を通じて現場力を底上げし、チームとしての連携を強化することで、問題解決能力が組織全体に浸透していきます。
研修やミーティングの場で、若手社員にも積極的に発言の機会を与え、「なぜこの作業が必要なのか」「どうすればより効率的にできるのか」を常に問いかける風土作りが重要だと考えています。加えて、失敗を責めるのではなく、“失敗から学ぶ”という姿勢を大切にしているため、新人や若手でも挑戦しやすい雰囲気が醸成されています。結果として、サプライチェーン全体を見渡せる多角的な視点を持つ社員が育ちやすくなり、“考える力”が自然と培われるのです。
働き方改革関連法によってトラックドライバーの時間外労働が制限される「2024年問題」は、物流コスト上昇や荷物の遅延リスクなど、業界全体に大きなインパクトを与えます。これに対し、小倉運送は早期からモーダルシフトやハイブリッド輸送を推進し、ドライバーの拘束時間を削減しています。
“問題解決能力”の視点で注目すべきは、「制約をどうプラスに変えるか」という発想転換です。規制強化を単なる負担増と捉えるのではなく、長距離輸送を船や鉄道でカバーすることでコストダウンと環境負荷軽減、さらには社員の労働環境改善を同時に実現しているのです。複数の利害関係を調整しながら最善策を編み出す、まさにコンサル的な手法が光る場面といえます。

小倉運送は製品を九州から関東へ運ぶ際、トラックではなく鉄道を活用するケースを増やしています。貨物列車の運行時間に合わせて出荷をコントロールし、着駅後は短距離トラックで関東圏の各拠点へ配送を行うというハイブリッド輸送を展開。ドライバーの長時間拘束を避けるうえで有効なだけでなく、燃料費や高速道路使用料の削減効果も高く、荷主企業の物流コストを大幅に圧縮できる可能性があります。
企業活動のなかで、社会貢献や地域連携はコスト要因と見なされがちですが、実は問題解決能力と相性が良いテーマです。小倉運送が所在する北九州市は、公害問題を克服して環境先進都市へと転換した経験を持ち、行政や地域企業との連携が活発です。こうしたバックグラウンドがあるからこそ、CO₂削減や災害時の緊急輸送など、社会課題の解決と企業のビジネスを結びつける取り組みが加速しています。
たとえば、地域が抱える過疎化や高齢化問題に対しては、物流網を活用して買い物弱者を支援する施策も考えられます。過疎地に住む高齢者が日用品を手に入れやすくなるよう、小倉運送はラストワンマイル協同組合などとの連携を通じて、少量多頻度の輸送を柔軟に組み立てる仕組みを整備。公共交通機関が限られる地域でも、必要な商品を届けることで、地域の暮らしをサポートする役割を果たしています。こうした取り組みは、企業の社会的評価にもつながり、地域に根差したビジネスモデルの強みをさらに高めることにも役立っています。
物流における問題解決は、ICTやAIの導入によって新たな局面を迎えています。配車管理や在庫最適化など、従来は人間の経験に頼っていた判断をデータに基づいて行うことで、精度やスピードが格段に向上するからです。
しかし、デジタル技術だけでは解決できない現場特有の問題も存在します。小倉運送は、データ分析で最適ルートや需要予測を算出しつつ、トラックドライバーや倉庫スタッフとの対話を重視し、最終的な調整を丁寧に行っています。人とシステムが補完し合うことで、万が一のトラブル時にも柔軟に対応できる“しなやかさ”を保つことができるのです。
近年、ECでの注文数が一時的に爆発的に増える“瞬間風速”が問題視されています。セールやイベントなどで予期せぬ需要が押し寄せると、在庫が枯渇したり、倉庫作業がパンク寸前に陥ったりすることがあります。そこで、AIを活用した需要予測モデルを導入し、過去の販売データや外部要因(天候、祝日、SNSのトレンドなど)を複合的に分析。リアルタイムで在庫補充や出荷計画の再調整ができるようにすることで、急激な需要変動にも冷静に対応できるようになっています。
ECの普及によって浮上したのが、“ラストワンマイル”の問題です。消費者の手元に商品が届く最後の区間は、道路渋滞や配達コスト増、人手不足など、多くの課題が凝縮されています。小倉運送は大手宅配業者や、ラストワンマイル協同組合との連携を深め、九州から関東、さらに地方都市へスムーズに商品を届ける“シームレスな輸送モデル”を実現しています。
ここで重要なのが、「全体最適をどう図るか」という視点です。自社だけで対処しようとすれば、コスト面でも人員面でも限界がありますが、協同組合や地域の運送会社とのネットワークを活用すれば、多拠点や多地域をカバーできる可能性が一気に広がります。問題解決能力とは、社外のリソースをうまく取り込み、相乗効果を狙う柔軟な思考でもあるのです。
ラストワンマイルの課題は都市部と地方で異なります。都市部では渋滞や駐車スペースの問題が大きく、地方では低密度地域への効率的な配送が難しいという課題があります。小倉運送はそれぞれの地域特性を踏まえ、電動アシスト自転車や小型EVなどの新しい輸送手段を模索したり、拠点をきめ細かく配置したりするなど、多角的な提案を行っています。協同組合と連携することで、同業他社とも協力し合い、宅配の効率を高めるWin-Winの環境づくりを進めているのです。
問題解決には、現場が持つ暗黙知や小さなアイデアが大きなカギとなることが少なくありません。日々の作業をこなすなかで、スタッフが感じる「ここが無駄ではないか」「こうすれば安全性が上がるのでは」という気づきが、やがて組織レベルのイノベーションにつながります。
小倉運送が現場と経営の距離を近づけ、提案をスピーディに実行できる風土作りを進めていくのは、こうした“草の根レベル”の課題発見と改善を重視しているからにほかなりません。多様なバックグラウンドを持つ社員がそれぞれの専門性を発揮し合い、互いのアイデアを尊重することで、新たな解決策が自然に生まれる環境を整えているのです。
SDGs(持続可能な開発目標)が世界的な潮流となるなか、物流会社にも環境負荷や地域社会への責任が強く問われています。実際、ドライバー不足や過度なCO₂排出は、持続可能性を損なう大きな要因です。小倉運送はモーダルシフトやICTの活用、社員の労働環境改善などを通じて、これらの問題に“具体的かつ実行可能な”解決策を提供し続けています。
重要なのは、こうした持続可能性をめぐる課題を、「社会的要請だから仕方なく取り組む」のではなく、「企業の競争力を高めるチャンス」として捉えている点です。環境に配慮した輸送を実現すれば、新たな顧客層の獲得やコスト削減にもつながり、結果的に経営が安定し、地域社会に還元できるリソースも増えます。問題解決能力を“未来への投資”として位置づける視点は、SDGs時代に大きく求められるアプローチといえます。

最近は“グリーンロジスティクス”という概念が広まり、CO₂削減のみならず排出物・廃棄物の削減やリサイクルの促進に取り組む事例が増えています。小倉運送は、地域と連携してサーキュラーエコノミー(循環型経済)の一端を担うことを視野に入れています。物流が単なる運搬業務にとどまらず、サプライチェーン全体の資源効率を高める存在として機能する――これこそがSDGs時代における先進的なモデルといえるでしょう。
ここまで紹介してきたように、小倉運送の“物流コンサル”は多様な領域で実践されており、その根底には確かな問題解決能力が存在します。では、この能力はどのように育まれているのでしょうか。
問題解決のプロセスは、一度で完結するものではなく、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を何度も回しながら継続的に改善していく点が重要です。小倉運送では、プロジェクトが終了したあとでも定期的にレビューを行い、新たな課題が生じていないか、既存の対策が陳腐化していないかをチェックしています。こうした“地道な検証と改善”の積み重ねが、企業全体のレジリエンス(変化対応力)を高める原動力となっているのです。
物流は、多種多様な業種の“縁の下の力持ち”として機能するだけでなく、課題解決の視点を取り入れることで社会全体を支えるインフラへと進化してきました。小倉運送の“物流コンサル”が示すように、“考え、つなぎ、整えながら課題を解決する”というアプローチは、企業のビジネス成長や働き方改革、さらには環境保護や地域活性化にも広く貢献します。
これからの時代は、AIやIoT、自動運転など新たな技術が次々と登場し、それに伴って新たな課題も浮上してくるでしょう。しかし、“問題解決能力”が確立していれば、どんな変化にも柔軟に対応し、むしろチャンスに変えることができます。物流業界のみならず、あらゆるビジネスや地域社会にとって、課題に取り組む姿勢こそが持続的な発展をもたらす鍵となります。
小倉運送は、現場で培ったノウハウと先端技術を組み合わせながら、既存の常識にとらわれない新たなチャレンジを続けています。その裏には、問題解決能力を磨く企業文化が根付いているからこそ、数多くの成功事例を積み重ねてきたのです。
“問題解決”という視点で物流を見つめなおすとき、私たちは社会インフラとしての物流の奥深さと、そこに広がる可能性を改めて感じることでしょう。企業や地域に存在する多様な課題を解決し、未来への道筋を切り拓く一助として、小倉運送の取り組みは今後も大きな注目を集め続けるに違いありません。
企業の課題解決は、単なるコスト削減ではなく、新たな価値創出や地域社会への貢献につながる可能性を秘めています。現場と経営、地域と世界を結びつける物流の力は、その可能性を大いに広げる鍵となるでしょう。問題解決能力こそが、物流の未来を開くための最強のドライバーなのです。